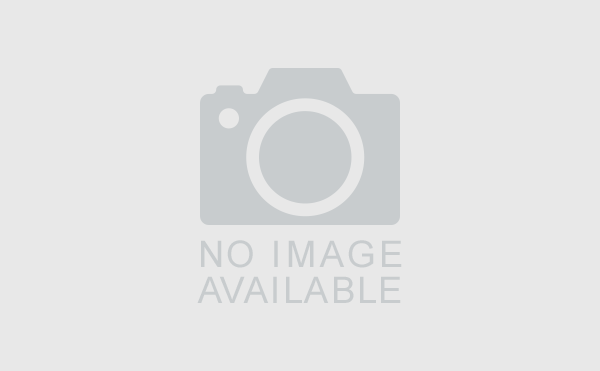ぜひ真似してほしい!釣り愛好家のために各地で行われている釣り促進方法

以前の記事でも触れた釣り場所について、無くなっていく場所もある一方で逆に釣りに対して寛容で釣りを発展させるための漁港や、釣りマナーの啓発活動を行っている地域や有識者の方がいます。
国内で行われているマナーを守って釣りを続けていくための一部の活動についてご紹介します。
[blogcard url=”https://seiro-nigiwaikan.jp/10548″]
釣り人マナー向上の啓発活動行う沖縄
出典:南国釣りコ
沖縄は海に囲まれた非常に釣りをするには良い環境に恵まれていますが、釣り禁止となってしまう港も少なくありません。そのため、沖縄では安全に快適に釣りを楽しむことができるよう釣り人同士のマナー向上に対する様々な努力を行っています。その1つが釣り人のマナー向上の勉強会です。日ごろ何気なく行っている釣りであっても、十分な準備をしなければ思わぬ事故やトラブルを引き起こしてしまう原因となることや、現在では釣りを黙認している旅行であってもこれらのトラブルが発生した場合にやむを得ず釣りを禁止しなければならない事態に陥ることなどを踏まえて、釣り人に対して必要な準備を確実に行うよう、その内容に関して勉強する機会となっているのです。自然と関わりのある釣りは非常に楽しいものですが、自然と関わるレジャーであるからこそ様々なトラブルを招く危険もあるため、事前に十分な準備をすることが必要となります。さらにその自然を維持するために最低限のマナーを守ることが快適にレジャーを楽しむことができる要因となるのです。
釣り文化振興促進モデル港という港

夜の下関港
漁港で釣りを行う文化を維持するためには、釣りをする人がその場所を利用するための基本的なマナーを遵守し、トラブルや事故を未然に防ぐための心構えを持つことが重要です。釣りは文化と言う面でも非常に効果的なものであり、様々な交流も生まれる機会が多いことから大切にしたいものですが、様々な交流も生まれる機会が多いことから大切にしたいものですが、そのために危険が伴ったり本来の漁港の業務を妨げるようなものであってはなりません。そのため国交省は1部の漁港に対して釣り文化振興促進モデル港と位置づけ、観光資源としての釣りを普及させるとともに、そのマナー向上や事故防止のための基本的な環境をモデル的に生み出そうとしています。青森港や山口県の下関港など全国の13カ所がこの釣り文化振興促進モデル港となっており、それぞれの場所で釣りを楽しむことができる環境を作りながら釣り人のマナーや危険防止を浸透させるものとなっているのが特徴です。
曖昧な釣り禁止看板の書き換えに動いたプロアングラー

東京湾を囲む湾奥内でも釣り禁止区域が増えていますが、看板に書かれている文言が禁止?一部禁止!?なのかわからないものが多く、結局釣り禁止と判断せざる得ない場所になってしまうことに目を付けたのは東京を拠点に活躍するシーバス釣り界において湾奥のカリスマと呼ばれたて久しい村岡昌憲さん(FimoやルアーメーカーBlueBlue代表)だ!
東京湾の一部の釣り場所を開放してもらう活動を行うために立ち上がってくれました。
実際に都民ファーストの会、都議会議員さんに直接相談。自ら代表を務めるFimoの事務局に本部を設置して活動をしてくれていました。
東京湾は公園利用者のうち釣り人に対しては排除的ではありません。釣り自体は認められる傾向がある。但し、他の利用者に危険が及ぶなら禁止する方向。 行政サイドは細かい事情まではわからないので、単純に「投げ釣り禁止」「ルアー釣り禁止」等の看板になりがちです。
出典:Fimo東京湾の釣り場を開放する動きを始めます
まとめ
こうしてみると一部の人たちには釣り人のマナーが悪いと攻撃を受けることがあっても、応援してくれる人もいます。ただ今回のこのような活動を見ていて真っ先に思うことは、有識者や地域団体が動いたところで私たち釣り人ひとりひとりが自発的に釣りマナーを守ることが一番重要だと感じました。