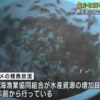ヒラメ釣りには潮の満ち引きが大きく関係してきます。過去にヒラメ釣りの際に残してきたデータを元に釣りやすい潮周りをわかりやすく解説していきます。
周期のある潮でいちばん釣果が上がった潮と、満干の差やヒラメが動くのは下げ潮か?上げ潮かなど疑問にお応えしていきます。

小学生の頃に釣りをしはじめルアーフィッシングに目覚める。釣り歴18年でIl Pescariaの番頭です。バス釣りからチニング、エギング、アジング、オフショアのライトジギング、チーバス(小さいシーバス…汗)で週3~4日はどこかにいますw 生涯で釣りに使ったお金はおおよそ軽自動車なら楽々新車で買えるほど投資しました。その経験と良いと思ったことはすぐに誰かに話したくなる性格(おせっかいでおしゃべり!?)を強みに日々魚と奮闘中!
釣りやすい潮の周期

ヒラメが釣りやすい潮を紐解く前に、より深く理解しやすくするために潮の周期について軽く触れていきます。
潮は1回の周期ので大潮、中潮、若潮、長潮、小潮を、それぞれ大潮が4日続いた後、中潮が4日間、その後に小潮が3日と続き、その後長潮、若潮、また中潮が2日あって元の大潮に戻る15日周期を繰り返します。
また1日の中で2回上げ潮と下げ潮を繰り返し、24時間経過すると次の潮へ移行します。
潮の満ち引きによって満干の差が大きい順に並べると
大潮>中潮>若潮>小潮>長潮
となり、左にいくほど潮の流れがはやく満干の差が大きくなっていく潮周りになります。それだけでいうと大潮がいちばん潮の動く潮と言うことがわかります。
「大潮が一番釣れる」はヒラメには当てはまらず
よくジギングなど回遊魚狙いでは潮が良く動く大潮の方がいいとか言われることもありますが、自分の経験上ヒラメ釣りの場合は当てはまるといえません。
大潮でベイトがぴちゃぴちゃいっていてボイルが起こっている状況も一瞬のうちに過ぎてしまったなんていうこと、皆さんも経験したことあるのではないでしょうか?
潮の動きが激しい分、豊富なベイトは入ってきやすいもののその都度行ったり来たりを繰り返しので行動範囲も大きくなり安定しません。
潮がまったく動かないよりは、動いていた方がベイトの量も多くなりヒラメの活性も高くなりやすく、より潮が動いている方が良いのは言うまでもありませんが、動き過ぎるとベイトもろとも「散っていく数も多い」ということ。
このあたりがヒラメの釣れる潮周りを見つけた大きな要因になりました。そこで釣果の都度メモしていたデータを元に割り出したヒラメが釣れる潮周りが判明しました。
安定してくる潮が狙い目
ヒラメが落ち着いていられる潮が、これまでの釣果データでわかってきたんです。
もっとも潮の流れが緩い長潮を起点として、潮の周期とヒラメの釣れる量を表にしてみるとこんな感じになります。
| ▲ ▲ |
▲ ▲ ▲ ▲ |
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ |
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ |
▲ ▲ ▲ ▲ |
▲ ▲ ▲ |
▲ ▲ |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 長 潮 |
若 潮 |
中 潮 |
中 潮 |
大 潮 |
大 潮 |
大 潮 |
大 潮 |
中 潮 |
中 潮 |
中 潮 |
中 潮 |
小 潮 |
小 潮 |
小 潮 |
ヒラメの数が少ないと感じた潮(釣果が振るわない潮)を■色で、たくさん釣れた潮を■色で、▲の数でヒラメが接岸してくるおおよその量を理解しやすいように形で表しています。
自分の経験から言うといちばんヒラメの量が多いと感じたのは若潮と、その直後の中潮2日間です。
大潮が4日続くより手前の中2日間の中潮の時が、いちばんヒラメが接岸している量が多くありました。その直前の若潮くらいから徐々に増え始め、その中潮の間、近辺に居着いていて、その後にくる大潮に乗って徐々にまた離れていくものと思われます。
潮が動かないとベイトも動かないためフィッシュイーターのヒラメも当然動かなくなると考えれますが、満干の差が激しすぎても全体の個体量が減っていくことを表していると思います。
このことで、【潮が緩やかに動きはじめるタイミング】が一番接岸していると仮説が立てられます。
大潮も本当は釣れるのでしょうが、時合が一瞬で終わったり、大潮の時ってポイントに人も多いのがネックとなるため、今では自分の場合、大潮を好んでヒラメ釣りに行ったりしてません。
潮が動くときはベイトや水温が安定しにくい
じゃぁ、これは通年通して言えることなのかという疑問が湧いてくるわけですが、
特に活性が高くなる夏などは潮の流れに差があったとしてもヒラメの個体数はあまり変わらない気もします。
しかし逆に、冬場など活性が低くなる時期ほどこの仮説があてはまるのではないかと思ってます。
これは潮の流れが速く水量の浮き沈みが激しくなってくると水温が安定しないためだと思われます。
冬場のヒラメは水温が安定しやすい(温かい)場所を好んで移動するため、潮の流れで攪拌されて水温が安定しない大潮などより、水温が安定しやすく、それでいて少しベイトが入ってくる若潮~中潮の潮周りが体力を温存しやすいと思うのです。
時間帯と潮の関係

ですがどの魚種の釣りにも共通することだろうと思うのですが、潮周りだけが釣れる釣れないを左右するわけではありません。当然時間帯も関係してきます。
ほかの章でも解説していますが、もっともヒラメが釣りやすい時間帯は「朝マズメ」です。
このことを考えると若潮~中潮の日の朝マズメはテッパン!?だといえそうです。
また、活性が低い冬の時期とかだと気温とともに日射しが水中を照らし始め水温が上がり始める朝マズメの終わり掛け~太陽が昇り切るまでの時間帯も狙い目となります。
ポイントも関係してくる
もちろん時間帯だけではなく、ポイントによっても差が出てきます。その場所の海底の地形や大きく入り込んだワンドなど外洋の潮目から離れている場所などは複合的な要素が合わさってきるので判断がより難しくなります。
それらは何度か潮周りの異なる日に通って見て、自分の目と頭で分析していくしかないです。
満潮、干潮のヒラメの動き

大抵は、潮が満ちてくると流れに乗って無数のベイトの群れとともにヒラメも浅瀬まで接岸してきます。また潮が引いてくるとベイトと一緒に沖へ流れていきます。
ただ、ドン深(急深)のサーフでは、足元付近で急に深くなっていて沖の方が瀬になっている場所とかは潮の流れに関係なく、そのブレイクに身を潜めてヒラメが溜まっている場合もあります。潮の満干でも顔を出さない瀬のことです。
ヒラメは上げ潮?下げ潮?どっちが釣れる?

潮の動きによって水量と水深が変化する満潮の時と、干潮の時のヒラメの動きは上で説明したとおり上げ潮で接岸。下げ潮で沖へ戻っていくので、「じゃ、釣れるのは上げ潮じゃないの」と思うかもしれませんが、
ここがまた釣りの奥深さ、ちょっとそれも違うんです!
実際自分は小潮のだだ引きのドシャローでもヒラメが釣れた経験があり、一概にどの潮がいいと断言できないポイントもあります。
上げ潮と、下げ潮どっちが釣れる?と聞かれると、釣れる確率的には上げ潮といえるかもしれませんけど…下げ潮でも釣れるんですw
どっちつかずのことしか言えなくてごめんなさいww
こういう一つの理論だけではわからないことが多いのが釣り。これがまたポイントへ行って確かめたくなるから釣りは辞められないのでしょうね。
簡単にわかってしまおうとおもしろくないですから。
ポイントに通い場所ごとの良い潮周りを見つけよう!
ここまでいろいろと説明してきたことを、最後にもう一度整理してみたいと思います。
自分のデータから言えることは潮の種類の中で、ヒラメがいちばん釣れると感じた潮周りは「若潮~その後2日間の中潮」ですすが、これも自分の個人的な意見です。目安として捉えて頂き実際に釣行してみて皆さんが行くポイントに当てはめながらいい潮を見つけてください!
「結局は人任せじゃねえか!」と叱られそうですが、つまるところそういいうことに成りますw(汗)
けど、今回お伝えしたことを元に次にヒラメ釣りに行くときの計画を立ててもらえると何かしら釣果が変わってくるのではないかと思っています。ぜひ活用してみてください!
釣りやすい潮周りは若潮~中潮の3日間
この3日間の朝マズメはテッパン!
当てはまらないポイントもある
確実な情報は自分の脚で探そう!